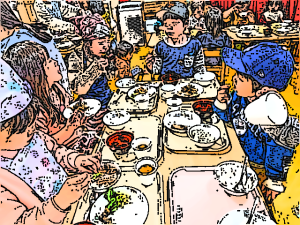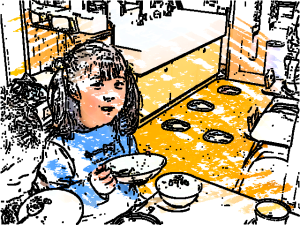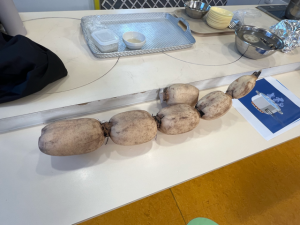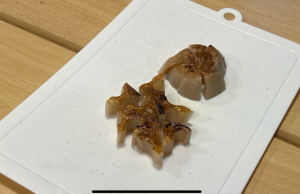私たちは食べ物を美味しいと感じる味覚を持っています。でも、その感じ方には、個人があります。自分が感じている味を人も同じように感じているとは限らないのです。この◯◯は美味しいね、と「同じであることを前提に」他者に同意を求めがちですが、実際はちがっているかもしれません。

そのことを、研究するために大妻女子大学の先生が園に来られたので、子どもたちの傾向と私たちの保育アプローチを説明しました。
人間の味覚は遺伝子の研究がすすみ、「苦味」のように遺伝的に明確に説明できる特性もありますが、「甘味」「旨味」「脂味」などは複雑に「遺伝+環境」の影響を受けているそうです。しかし、実際のところはまだよくわかっていません。味覚の感度が高ければ、少しの刺激でより多くの感覚情報を得ていることになります。それが食べ物の好き嫌いの傾向にもつながっているだろうことは、容易に想像できます。
人間以外の動物の味覚を考えてみると、味を感じる味蕾の数は動物によってかなり差があり、それらの好む食べ物の傾向が現れています。竹の味をパンダはどのように「美味しい」と感じているのでしょう? ということです。下等動物から人間まで共通するのは、顔には口があるということで、外部から栄養を摂るための口が必ずあっても、その味の感度の差は、獲物を得るための手段として発達しています。
このように知覚は生存のための行為に直結しているからこそ、その「種」の特性が知覚の特性と相関しています。その動物の生き方やライフスタイルが、どの動物の知覚と行為の相関特性を作っています。
私は点字が読めませんが、読める人は読めない人よりも、指の感覚が鋭いといえます。犬の嗅覚は人間のおよそ1万倍〜1億倍とも言われています。犬の鼻には嗅細胞が約2億個(人間は約500万個)もあるそうで、微量なにおい成分も識別できます。犬種や個体差にもよりますが、警察犬や災害救助犬などのことを思い浮かべるだけでも、その精度の高さに納得します。
同様に5月に上野動物園でもみたコウモリは人間の数百倍以上の精度を持っていると考えられています。特に「超音波(20kHz以上)」と言われる、私たちには聞こえない高周波の音まで感知できます。また、コウモリは「エコーロケーション(反響定位)」という能力を使って、自分の発した音波が物体に当たって返ってくる反響を聞き取ることで、暗闇の中でも障害物や獲物の位置を正確に把握しているので、暗闇の飛行でもぶつかることがありません。
タカやワシなどの猛禽類は視力が優れており、1キロ先の獲物もはっきり見えているというから驚きです。しかもあのスピードで滑空しながら海面の魚や地面の小動物を掻っ攫っていく芸当は驚異的です。また昆虫の蝶も人間には見えない紫外線を含む色調を区別しており、花の色による「ガイドマーク」によって蜜の場所をみつけることができるそうです。
さて、人間はなんでも食べますが、そもそも「味わう」や「なんでも食べられるようになること」に、どれだけのこと期待をしていいものなのか。平均値からずれているからといって、その知覚を過敏だという言い方も、かえって鈍感な言葉の使い方かもしれませんね。

















-225x300.png)